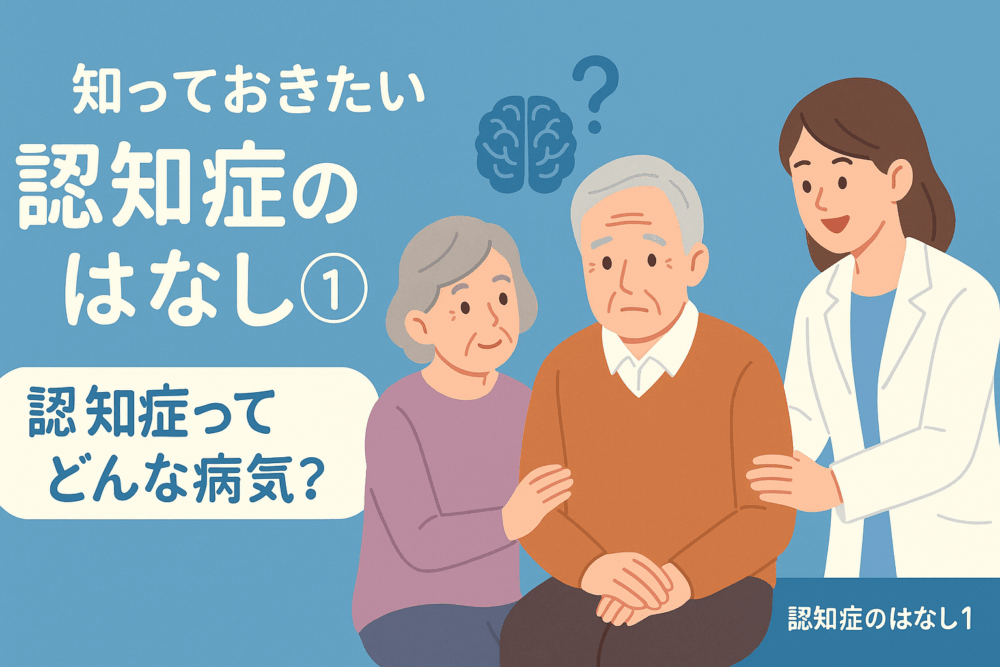皆さんは日常生活で「認知症」という言葉をよく耳にするかもしれません。
しかし、いざ「認知症ってなに?」と聞かれると、きちんと説明できるでしょうか?
日本ではこれから2040年に向けて超高齢化が急速に進みます。
身内で認知症の方を介護するご家庭も増えていくと予想されます。
これから連載予定の記事では「認知症」を少しずつ、ゆっくりと、分かりやすく紐解いていきたいと考えております。これから紹介予定の記事が皆さまの「認知症」について理解を深める一助となれば幸いです。
認知症って何?
認知症は、病気やケガ、障害で脳に障害やダメージが生じ、記憶力や判断力といった認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。
記憶力や判断力の認知機能の低下とは、ちょっと前に自分がした行為を忘れたり、時間や場所が分からなくなったり、人を認識できなくなったり、今まで出来ていたことが難しくなったりする状態などが継続的に続くことです。
認知症は症状の総称です
実は、「認知症」というのは1つの病気の名前ではなく、さまざまな原因によって起こる症状の総称です。認知症を引き起こす原因となる疾病の代表的なものとして、以下の4つの種類があります。
[box class=”yellow_box” title=”代表的な4種類”]
- アルツハイマー型認知症
- 血管性認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症[/box]
これらの種類の特徴については、次回以降の記事で詳しく解説していきます。認知症は1つの病気ではないため、症状もさまざまであることを頭に入れておくとよいでしょう。
つぎに、それぞれの種類が認知症全体に占める割合と、男女の罹患比率を簡単にご紹介します。
| 認知症の種類 | 全体に占める割合 | 男女罹患比 |
| アルツハイマー型認知症 | 約7割 | 女性のほうが多い |
| 血管性認知症 | 約2割 | 男性のほうが多い |
| レビー小体型認知症 | 1割未満 | 男性のほうが多い |
| 前頭側頭型認知症 | 1割未満 | ほぼ同じ |
※出典:性差と認知症 最新精神医学2024 鳥取大学医学部、都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応(厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野認知症対策総合研究)などを参考に作成
上記割合や比率は、調査や研究によって多少異なる場合があります。
私は認知症になる?ならない?
認知症はメカニズムが解明されていないものが多く、誰にでも起こりうる可能性があります。年齢が上がるにつれて老化現象と共に罹患する割合は高くなりますが、若い世代でも発症することがあります。以下に、認知症患者数の年齢別罹患割合の目安を示します。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
| 65歳~69歳 | 2.8% | 3.8% |
| 70歳~74歳 | 4.9% | 3.9% |
| 75歳~79歳 | 11.7% | 14.4% |
| 80歳~84歳 | 16.8% | 24.2% |
| 85歳~89歳 | 35.0% | 43.9% |
| 90歳~94歳 | 49.0% | 65.1% |
| 95歳以上 | 50.6% | 83.7% |
※出典:厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業報告書(研究代表者:朝田隆. 2013年)より抜粋
これらの数字を見ると、年齢とともに認知症のリスクが高まることが分かります。しかし、これはあくまでも統計的な割合であり、すべての方が当てはまるわけではありません。
「家族のかたが認知症かも?」と思ったら
もし、ご家族の方の様子を見て「もしかしたら認知症かもしれない」と感じたら、まずは専門機関に相談することが大切です。早期に相談することで、適切な診断とサポートを受けることができます。相談窓口としては、以下のような機関があります。
[box class=”box”]
- 地域包括支援センター:高齢者やその家族の総合的な相談窓口です。認知症に関する相談や、適切な医療機関・介護サービスの紹介などを行っています。
- 認知症専門医:専門的な医療相談や診断、治療、情報提供などを行っています。
- かかりつけ医:まずは身近な医療機関であるかかりつけ医に相談することも可能です。必要に応じて専門医を紹介してもらえます。[/box]
これらの窓口では、専門の相談員や医療従事者が、ご本人やご家族の状況に合わせてアドバイスや支援をしてくれます。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。
病院へ連れていくための自尊心を傷つけないアイデア
認知症の疑いがある方を病院に連れていくことは、ご本人にとっては抵抗がある場合も少なくありません。なぜなら、認知症だからといって、いきなりすべてが分からなくなることはなく、ご本人は分かっていることのほうが多いからです。
ここでは、ご本人の自尊心を傷つけずに、スムーズに受診してもらうためのアイデアをいくつかご紹介します。[box class=”box”]
- 「最近ちょっと頭痛がするから、お母さんも一緒に診てもらわない?私も歳だから、お母さんに付き添ってもらうと安心だわ」のように、ご自身の体調不良を理由に誘ってみる。
- 「お父さん、今年の健康診断は受けた?よかったら今年は一緒に受けに行こうよ」と定期的な健康チェックとして促す。
- ご本人が病院へ薬をもらいに行く時期を把握しておき、かかりつけ医に先回りで家族が連絡しておく。
- 「最近、あまり元気ないようだけど大丈夫?私も安心したいから一緒に病院へ行く?」と心配している気持ちを伝えて誘ってみる。 [/box]
大切なことは、ご本人の気持ちに寄り添い、不安や抵抗感を和らげる言葉がけをすることです。焦らず、根気強く、丁寧に話してみましょう。
今回の記事では、認知症の基本的な情報について解説しました。次回は認知症の代表的な4つの種類について、さらに詳しく掘り下げていきます。
[template id=”2702″]